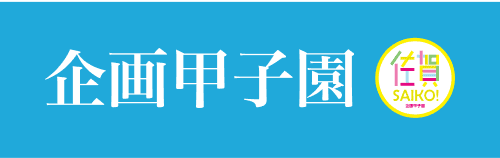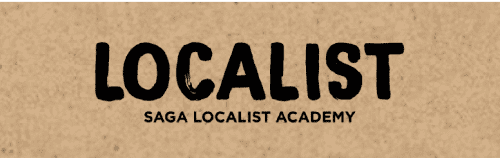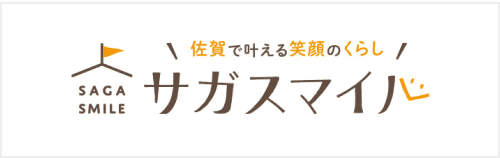佐賀県全域で活動する地域おこし協力隊「SAGA MEDIUM LAB.」(通称「SML」)の皆さんが約3年間の任期を満了するにあたり、
活動の集大成となる報告会を2025年2月4日に開催しました。
当日はお世話になった地域の方など、なんと100人を超える方にお越しいただきました。
その様子をレポートします!😊
1.堀江 恵さん
ミッション:佐賀県の公園マップを作ろう!「子どもとおでかけ編集室」
トップバッターを務めた堀江さんの発表テーマは「佐賀でレベルアップした3年間」。
佐賀県内の親子で楽しめるおでかけスポットの発信をされてきました。
1年目からインスタグラム「子どもとおでかけ編集室」で様々な情報を発信。
県内各地を取材しながら、画像編集にも取り組まれました。
2年目からはインスタグラムに投稿する動画の編集なども行うように。
それと並行して、冊子の取材・撮影をスタートさせたそうです。
3年目には冊子の編集・ライティングなども行い、おでかけスポットをまとめた冊子「OoSAGA(おぉさが)」が完成!
冊子の中には佐賀らしさや読者がイメージしやすい工夫など、堀江さんのこだわりがたくさんちりばめられています。
堀江さんのスキルアップの裏にはきっと、相当な努力があったんだと感じました。

「OoSAGA」は県内各地の児童センターや図書館、子育てイベントで配布されるほか、以下のサイトでも読むことができます。是非ご覧ください!
関連リンク:佐賀県を遊びつくす!おでかけブック OoSAGA(おぉさが)完成!
2.草田 彩夏さん
ミッション:こどもが笑顔になれる空間を!「こどもの居場所立ち上げサポーター」
次に草田さんが「わたしが“こどもの居場所”の景色から教えてもらったこと」をテーマに発表されました。

草田さんが着任したころは、県内にこどもの居場所がない市町もある状況。
そこから、こどもの居場所に関わる多くの人との対話を重ね、いまでは県内すべての市町にこどもの居場所ができています。
常に「私にできることはなにか」「誰のための居場所なのか」と自問し続けながら、こどもの居場所が地域に多様にあることを目指して活動したそうです。
草田さんは地域の皆さんや職場の上司・同僚、SMLメンバーから「エンパワー(※)」してもらったと言われていましたが、きっと周囲の皆さんはそれ以上に、草田さんにたくさん「エンパワー」してもらったのだと思います。
草田さんの報告を聞いていた皆さんからのたくさんの感謝の言葉が、そのなによりの証でした。
※社会の中にある差別や偏見を取り除き、その人が持っている本来の力や可能性を引き出すこと。
関連記事:
「わたしがつくる、さが #4 草田彩夏さん(こどもの居場所立ち上げサポーター)」
3.木村 瑠々花さん
ミッション:公共交通をよりよくする仕事「くらしのモビリティサポーター」
木村さんの活動は、コミュニティバスや住民同士の共助交通、乗合タクシーなど、住民さんの「生活」に密着している交通手段を一緒に考えていく「くらしのモビリティサポーター」。

佐賀県は言わずもがな車社会ですが、車に乗ることのできない人や車をもっていない人も安心して生活できるためには、地域交通の存在は欠かせません。ただ、自家用車の利便性を身をもって知っている地域の皆さんには、そうしたことを自分のこととして考えるのは至難の業。
そこで木村さんは、対話する相手の関心のレベルに応じたアプローチが必要であること、「地域交通への深い造詣」ではなく「人との対話」がなにより大事ということに気づいたそうです。
そうした対話を重ねた結果、県内各地にキーパーソンが増え、様々な動きが出てきています。
答えのない「地域交通」というテーマを通じてたくさんの対話を重ねてきた木村さん。困難なことも多かったと思いますが、この貴重な経験をきっと、これからいろいろな場面で活かしてくれるはずです。
4.長塩 千夏さん、長谷川 晶規さん
ミッション:島の記憶を記録に残す「七つの島の聞き書きすと」

午前中のラストを飾ったのは長塩さんと長谷川さん。小川島に実際に住みつつ、これまで島で大切にされてきた歴史・文化・食、そして島民の皆さんの思い出を聞き、それを記録としてまとめていくという活動をされてきました。
着任して日が浅いころは不審がられることもあったそうですが、徐々に島の人たちに認知してもらい、写真を提供いただく機会も増えたとのこと。
そして3年目、いよいよ「七つの島の聞き書きアルバム」の制作に着手。島の皆さんから提供いただいた膨大な写真やエピソードをどのようにまとめるのか、大変な悩みがあったそうです。
(本が一冊できるほどのエピソード、どれくらいの量があるのか想像もつきません…)
その中で言われていた「編集は独裁である」という言葉がとても印象的でした。
長谷川さんの目には涙が。一方、長塩さんは終始ニコニコ。対照的な(?)2人のキャラクターが、会場に温かさと明るさをもたらしていました。
5.日髙 涼子さん
ミッション:山菜をおいしく学んで、おいしく伝える「山菜料理人見習い」

日髙さんは山菜を代表とする里山の食を通じて里山のファンを増やす活動をされてきました。
活動を始めてすぐ、佐賀は冬場でも野菜が豊富にあるため、山菜文化はそこまで発展していないことが分かり、また、山菜をどのくらい採っていいのか?など、多くの疑問や課題に直面したそうです。
そこで日髙さんは里山で採れる山野草にも目を向けることにし、佐賀市富士町にある「森の香 菖蒲ご膳」をはじめとした県内外の多くの方からまなびを得ながら、なんと県内で2人目の「山菜アドバイザー」の資格を取得!
日髙さんは活動してきた3年間を振り返り、SMLの目指す「Medium(媒介する人)」になれたのか自信がない、と思われたとのこと。
しかし、自主企画イベントや活動報告会では、多くの人がお越しになり、日髙さんを囲む大きな輪ができていました。日髙さんが多くの人をつないでいたことは間違いなさそうです。
関連記事:
「わたしがつくる、さが #2 日髙涼子さん(山菜料理人見習い)」
6.天野 貴博さん
ミッション:登るを仕事に!「低山トレッキングガイド見習い」
「低山トレッキングガイド見習い」として活動されてきた天野さん。「見習い」とありますが、登山ガイド資格をお持ちの、いわばプロ。どんなに低山であっても、約20㎏のザックを背負い、色々な状況に対応できるよう備えているそうです。
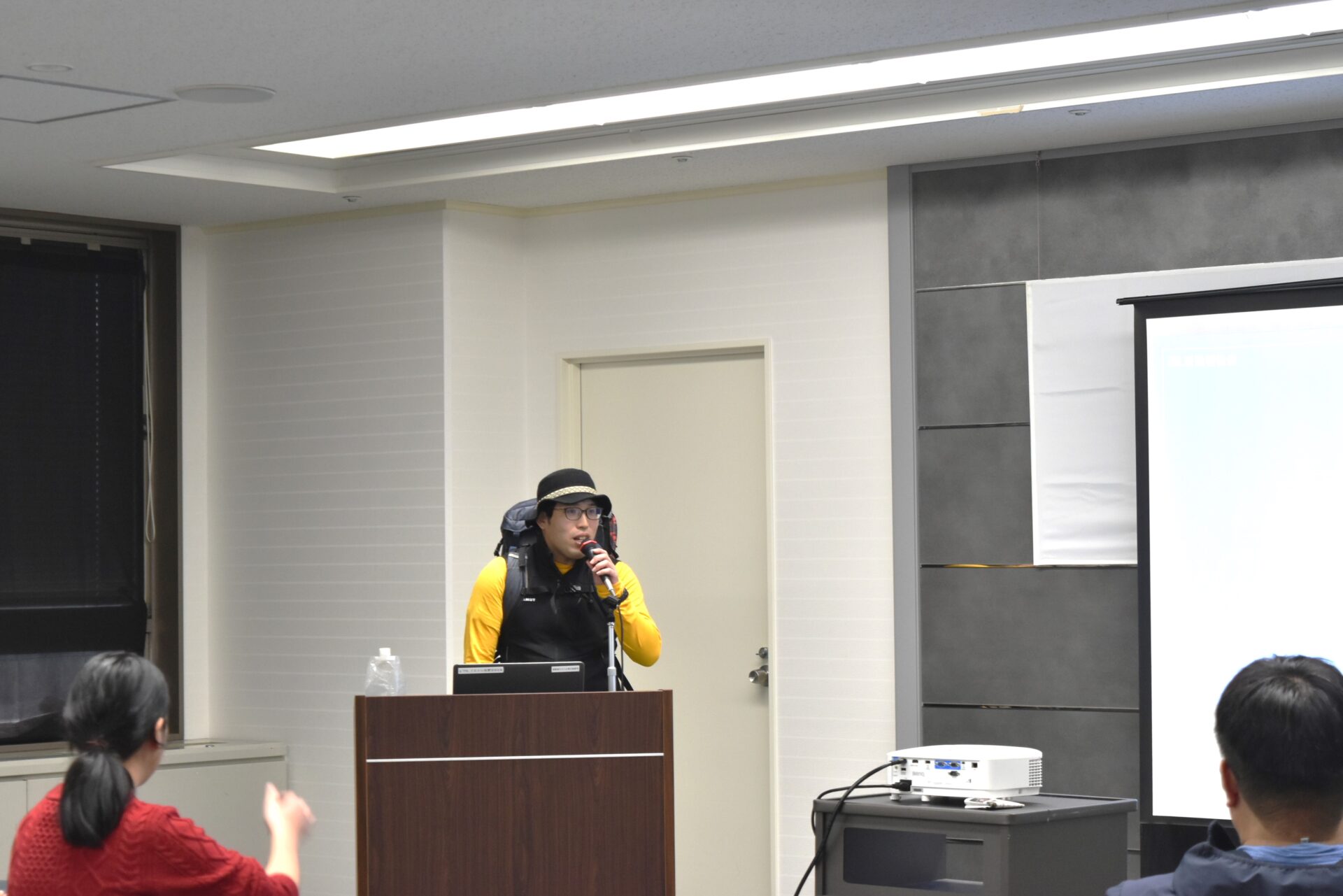
3年間の活動期間で案内した人数は延べ600人以上、総歩行距離は約530㎞、獲得した標高はなんと40,000mにもなるとのことで、ただただ驚くばかりです。
ガイドだけではなく、勉強会を通じてそのスキルをさらに周囲の人に広めたり、さらには登山道の整備や山の環境保全、マウンテンバイクやカヌーなどのアクティビティガイドと、幅広く活動されたそうです。
また、伴走した職員との友情には思わず胸が熱くなりました…!
ますます活躍の場を広げていかれるであろう天野さん。佐賀のアウトドアシーンに欠かせない人物と言われる日も、そう遠くはありません。
7.武田 有里子さん
ミッション:地域と外国人を結ぶ「多文化コミュニケーションプランナー」
「「多文化共生」とは?交流とは?考え続けた3年間」をテーマに発表された武田さん。佐賀に来る前はドイツでお好み焼き屋の副店長をされており、 “外国人”として暮らしてきた経験を、今度は大好きな佐賀の地で活かしたいという思いで、このミッションに応募したとのこと。

いざ活動を始めてみると、期間限定で来日している方も多いため、地域の方の中には「交流しても虚しいだけ」と考えている人もいることが分かりました。
そこで武田さんは「ここを離れる人がいても、新しく来る人はいる。その人たちのために、交流の機会を作っていく」と考え、国際交流ワークショップなどのイベントを企画したそうです。
話したいことがありすぎたのか、時間が足りず最後のあたりは駆け足になってしまいました。
でもそれはきっと、「多文化共生」というテーマに正面から向き合って活動してきた武田さんの、ひたむきさを表すものなのだと思いました。
8.古泉 志保さん
ミッション:CSO 連携型地域おこし協力隊「さがむすび隊」

「社会のお困りごとの種をなくし、誰もが幸せに暮らせる社会を目指す」活動をしてこられた古泉さん。
なんと、着任後すぐにウクライナからの避難民の受入れ・支援を行う「SAGA Ukeire Network」の立ち上げに関わることに。誰も経験したことのない対応や膨大な事務作業に奮闘されました。
その後、避難民の自立・定住に向けたウクライナ理解講座や、異文化への理解を深める「世界のお茶会」を開催したり、「Mimosequal(ミモザイコール)」という女性が自由に活躍できる社会を目指す団体を立ち上げるなど、本当に精力的に活動されてきました。
卒業後は多文化共生やジェンダーについての考えや思い込みを考え直すきっかけを作るため、講師・コンサルとして活動していくそうです。
協力隊の活動を通じて、たくさんの気づきを与えてくれた古泉さん。これからも多くの気づきをもたらしてくれることでしょう。
9.野見山 茂さん
ミッション:CSO 連携型地域おこし協力隊「さがむすび隊」
報告会のトリを飾ったのは「さがむすび隊」の野見山さん。

初年度はとにかく多くの場に顔を出すことを意識し、年に1,000枚もの名刺交換を通じ、ネットワークを構築されました。また、防災士など10個の資格取得をされたそうです。
2年目には「一緒にやる」ことを意識。多くの団体と被災地支援やゴミダイエット作戦、酒蔵跡のアートスペース化など、幅広い活動をされてきました。
そして3年目。これまでの2年間で見えてきた課題として、CSOの資金調達の難しさがありました。そこで野見山さんは、CSOを「推す」という発想「ファン度」を加えた「ファン度レイジング」を提唱し、多くの人・モノ・お金を結び付けてきました。
野見山さんは卒業後も引き続き「ファン度レイジング」を結び付けていくそう。
底抜けのパワフルさで県内外を駆け回られる様子、目に浮かぶようです。
結びに
隊員さんが発表されたあと、参加者から隊員さんへ、たくさんの感謝の言葉が紡がれました。参加者が涙で言葉に詰まる場面もあったりと、本当に心温まる会となりました。
協力隊の活動は「地域」「行政」「隊員」の三者それぞれにメリットのある「三方よし」となることが大事と言われます。この報告会には全然収まりきれないほどの盛り上がりから、10人の隊員全員がそれぞれの「三方よし」を実現していたことが伝わってきました。

この経験を糧に、さらなるご活躍をされることでしょう。
隊員の皆さん、本当にお疲れ様でした!
おわり